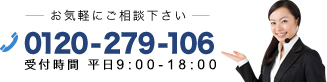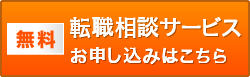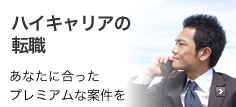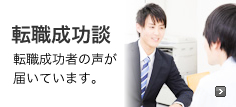注目されるワークライフバランス
転職雑記 2023/7/13

近年、日本では転職は当たり前の時代になりつつあります。働き方は多様化し、人生のキャリアの描き方は人それぞれになってきています。
当然、仕事だけでなくプライベートの充実も重視されるようになり、「ワークライフバランス」という言葉がよく聞かれるようになりました。
今回は、いまさら聞けない「ワークライフバランス」について、どのようなものなのか確認したいと思います。
1.「ワークライフバランス」の意味
「ワークライフバランス」とは「仕事と生活の調和」を言いますが、「仕事よりもプライベートを優先させる」「仕事時間と生活時間を均等にする」「時間以外の仕事はなるべくしないこと」といった誤った解釈をしている人も多いようです。
本質的には『仕事と生活が調和することによって好循環が生まれる』という能動的な状態を指します。
例えば、仕事の効率化で勤務時間が短くなれば、プライベートを充実させることにつながります。
それにより、仕事へのモチベーションが上がり、新しいアイデアや好成績が生まれやすくなり、結果仕事の質も向上するという好循環が期待されるのです。
欧米では既に1980年代からこうした考え方に取り組んでいました。
近年日本でもようやく『働き方改革』の実施により、『ワークライフバランス』は注目されるようになりました。
2.「ワーク・ライフ・バランス」憲章
政府が平成19年(2007年)に策定した「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」では、仕事と生活の調和が実現した社会とは、
「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」
と定義しています。
具体的には…
①就労による経済的自立が可能な社会
経済的自立を必要とする者とりわけ若者がいきいきと働くことができ、かつ、経済的に自立可能な働き方ができ、結婚や子育てに関する希望の実現などに向けて、暮らしの経済的基盤が確保できる。
②健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会
働く人々の健康が保持され、家族・友人などとの充実した時間、自己啓発や地域活動への参加のための時間などを持てる豊かな生活ができる。
③多様な働き方・生き方が選択できる社会
性や年齢などにかかわらず、誰もが自らの意欲と能力を持って様々な働き方や生き方に挑戦できる機会が提供されており、子育てや親の介護が必要な時期など個人の置かれた状況に応じて多様で柔軟な働き方が選択でき、しかも公正な処遇が確保されている。
このような社会を目指すべきだとしています。
3.ワークライフバランスが注目される理由
では、なぜ「ワークライフバランス」が注目されるようになったのでしょうか?
そこには、「働き方改革」など日本の労働環境に生じている様々な歪みを修正しようという試みがあります。
労働環境における主な問題を挙げてみましょう。
①少子化の急速な進行
既に1980年代後半から上昇し始めた「少子化」に対し、「ワークライフバランス」の推進は、出産・育児による離職防止や出産を諦めることを防ぐうえで極めて重要です。
②仕事と家庭の両立が困難
女性の社会進出が進んでいますが、「男性は仕事、女性は家庭」といった固定観念はまだまだ根強いものがあり、女性が出産・育児に伴って仕事を辞めなければならない場合が多いのが現実です。そのため、女性が仕事と家庭の両立を実現させるための制度を整備する必要があります。
③長時間労働による心身の健康への悪影響
不安定な非正規雇用の労働者が増える一方、人手不足による正社員の長時間労働の問題も残っています。過度な残業による精神的・身体的な不健康は、病気や自殺につながりかねない問題です。こうした悪循環を断ち切るためにも、ワークライフバランスの重要性が認識されつつあります。
④人材の確保
企業の発展には優秀な人材の確保が欠かせませんが、ワークライフバランスの良い企業に人材が集まる時代です。
離職率の低下を防ぐためにもワークライフバランスは企業にとって重要であると言えます。
4.コロナ後のワークライフバランス
「ワークライフバランス」は、新型コロナ禍以降再び注目が集まっています。
働き方改革が推進される中、大きく変化したコロナ禍以降の働き方について、企業は働き方の選択肢を増やし、従業員の生活の充実をサポートすることが重要になっています。
従業員も心身の健康を維持して行けば良いパフォーマンスを発揮できます。
この好循環を意識してワークライフバランスを追求していくことが大切だと言えるのです。