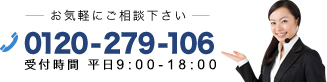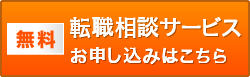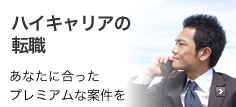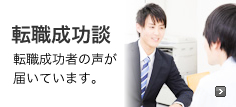扶養控除と税制改正とは
転職雑記 2025/10/28

「扶養内で働きたい」「◯◯万円を超えると扶養から外れてしまう」といった声をよく耳にします。
しかし、配偶者控除との混同などもあり、実際に扶養控除の内容を正しく理解している方は意外と少ないかもしれません。
そこで今回は、意外とわかりにくい「扶養控除」について、令和7年度税制改正の情報も踏まえて解説します。
制度を正しく理解し、税金や控除の取りこぼしがないようにしましょう。
1.扶養控除とは?
「扶養」とは、納税者が配偶者や子ども、親などを経済的に支えることを指します。
「扶養控除」は、扶養している親族がいる場合に、納税者の所得から一定額を差し引ける所得控除制度です。これにより所得税や住民税の負担が軽減されます。
会社員の場合、毎年「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出することで、自動的に控除が適用されるケースがほとんどです。
なお、配偶者がいる場合には、その配偶者の所得に応じて「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象になることがあります。
2.扶養控除額について
控除される金額は、扶養親族の年齢等により異なります。
・16歳以上19歳未満、および23歳以上70歳未満:38万円
・19歳以上23歳未満(特定扶養親族):63万円
・70歳以上(同居老親等):58万円
・70歳以上(同居でない):48万円
※「同居老親等」とは、納税者またはその配偶者の直系尊属で、常に同居している方を指します。
長期入院中であっても「同居」とみなされる場合がありますが、老人ホームなどに入所している場合は除外されることがあります。
3.扶養控除と配偶者控除・配偶者特別控除の違い
いずれも所得控除ですが、対象となる人物に違いがあります。
・扶養控除:配偶者以外の16歳以上の親族(子、親、祖父母など)
・配偶者控除:配偶者の所得が一定以下(合計所得金額58万円以下/給与収入のみなら123万円以下)
・配偶者特別控除:配偶者の所得が58万円超~133万円以下(給与収入123万円超~201万5,999円以下)
・また、いずれの控除も、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。
4.税制改正による変更点(令和7年度)
令和7年度税制改正案において、所得税の基礎控除額が引き上げられることが予定されています。
これに伴い、いわゆる「年収の壁」も見直される方向です。
〇年収103万円の壁が123万円に
従来、給与収入が103万円を超えると所得税が課税されるとされていましたが、基礎控除の引き上げにより、そのラインが123万円に引き上げられる見込みです。
つまり、給与収入が123万円以下であれば、所得税が発生しないケースが増えることになります。
〇年収150万円以下で非課税となる場合も
給与所得控除55万円+基礎控除95万円=150万円という非課税枠により、給与収入が150万円以下であれば所得税がかからない可能性があります。
〇特定扶養控除の見直し
19歳以上23歳未満の扶養親族(主に大学生など)に対する「特定扶養控除」についても見直しが行われ、年収150万円までであれば扶養控除の対象になり得るという方向で改正が進められています(2025年11月時点での案段階)。
5.扶養控除のメリットと注意点
〇メリット
所得控除によって税負担が軽くなる
健康保険の扶養家族にすることで、保険料負担が軽減される場合がある
〇注意点
扶養に入れたことで生活費等の実質的支援が必要となり、家計負担が増える可能性もある
親を扶養に入れると、介護保険料が高くなることがある(同一世帯に住民税課税者がいると保険料が増える場合がある)
6.まとめ
扶養控除は、扶養親族の所得や年齢に応じて適用される所得控除制度で、節税効果の高い制度です。
令和7年度税制改正により、給与収入ベースでの「年収の壁」が緩和され、より柔軟な働き方がしやすくなると見込まれます。
特に大学生などが扶養控除を意識して働き控えをしていたケースでも、今後は一定の収入があっても扶養控除の対象となる可能性があります。
ただし、実際の控除適用の可否は扶養親族の「合計所得金額」で判断されるため、最新の制度内容を踏まえたうえで判断することが重要です。
制度を正しく理解し、損のない形で活用しましょう。