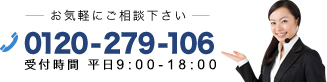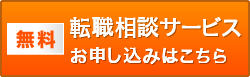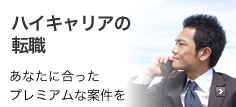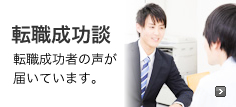祝日と祭日の違い
転職雑記 2023/8/15

日々仕事に励んでいる社会人なら、誰もが楽しみにしている休日。「あと○日働いたらお休み」と頑張っている人も多いことでしょう。
この休日について、「祝日」や「祭日」という言い方をする場合があります。
どちらも同じことにも思えますが、この2つは何が違うのでしょうか?
普段、何気なく使っている「祝日」と「祭日」ですが、実はまったく意味が違うようです。
1.休日は3種類
「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)では、日曜日以外の休日は「国民の祝日」「振替休日」「国民の休日」の3種類が規定されています。
- 国民の祝日
国が定めた「元旦」や「成人の日」など、仕事や学校が休みになる日
- 振替休日
日曜日が国民の祝日に重なった場合、代わりに休みになる日
(※民間企業には適用されないため、行事の都合で出校日にする学校や業務内容の関係で休日としない会社もあります)
- 国民の休日
祝日ではないが休みになる日(休日で挟まれている平日が休みになる日)
「祝日」は国の法律で定められた休日で、「国民の祝日」というのがその正式な名称となります。
「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)」の第一条では、
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、
よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、
又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
としています。
さらに、第二条では「国民の祝日」が列記してあり、現在の国民の祝日は1年間で16日あります。
1月1日の「元日」、2月11日の「建国記念の日」のように日にちが固定されているものもありますが、「成人の日」や「海の日」のように「○月の第○月曜日」とし、その年により日付が変わる祝日もあります。
また「春分の日」と「秋分の日」は、具体的な月日は法律で定められておらず、天文学上の言葉である「春分日」と「秋分日」とされています。
このため国立天文台が太陽の位置などから計算で「春分日」と「秋分日」を決め、毎年2月に公表される「暦要項」で翌年の「春分の日」と「秋分の日」の日付が記載されて日にちが確定します。
【令和5年(2023年)の「国民の祝日・休日」】(内閣府HPより)
| 元日 | 1月1日 |
| 休日 | 1月2日(祝日法第3条第2項による休日) |
| 成人の日 | 1月9日(1月の第2月曜日) |
| 建国記念の日 | 2月11日 |
| 天皇誕生日 | 2月23日 |
| 春分の日 | 3月21日 |
| 昭和の日 | 4月29日 |
| 憲法記念日 | 5月3日 |
| みどりの日 | 5月4日 |
| こどもの日 | 5月5日 |
| 海の日 | 7月17日(7月の第3月曜日) |
| 山の日 | 8月11日 |
| 敬老の日 | 9月18日(9月の第3月曜日 |
| 秋分の日 | 9月23日 |
| スポーツの日 | 10月9日(10月の第2月曜日) |
| 文化の日 | 11月3日 |
| 勤労感謝の日 | 11月23日 |
2.日曜日について
日曜日の由来がキリスト教由来であることは有名ですね。起源もローマ時代に遡ります。
日本で日曜休みが始まったのは1876年(明治9年)。
欧米との交易に不便があったため、欧化政策の一環として欧米に合わせる形で土曜半休、日曜休日制が導入されたと言われています。
官公庁の休日に則って休みを設けていた市町村役場、初等学校などを通じて地方に普及し、日曜日が休日であると認識されて現在に至っています。
しかし、日曜日を休日と定める法律は「国民の祝日に関する法律」(祝日法)には無く、別に「国会に置かれる機関の休日に関する法律」「裁判所の休日に関する法律」「行政機関の休日に関する法律」があり、行政機関・裁判所などの当該機関の休日を日曜日(および土曜日・祝日・指定された日)と定めているだけです。
官公庁が休みとされているため、一般的なカレンダーでも日曜日が赤く休日扱いになっていますが、法律上では日曜日が休日とされているのは限定的と言えます。
実際、民間企業にも適用される「労働基準法」においては休日に関する具体的な曜日は指定されておらず、祝日法の振替休日の規定も民間企業には適用されていないため、企業や業界によっては日曜日が休日ではない所も少なくありません。そうした業界のカレンダーでは日曜日が赤い休日になっていない場合もあります。
4.「祭日」は無くなった!?
暦の上で休日となっている日を「祝日」「祭日」、あるいは「祝祭日」などと言いますが、実は休日における「祭日」や「祝祭日」は俗称で公式の休日としては存在していません。
「祭日」は、昭和22年(1947年)に皇室祭祀令が廃止されるまでは、皇室の儀式や祭典を行われる宮中祭祀日を指し、祝日とともに国家の休日とされていました。
しかし、「国民の祝日に関する法律」が制定された昭和23年(1948年)以降は、祝日については「祝日」もしくは「国民の祝日」が正式になっています。
ただし、休日における「祭日」は無くなりましたが、皇室儀式は継続しているので、宮中祭祀が行われる日としての「祭日」はあると言えます。
また、11月23日の「勤労感謝の日」(新嘗祭の日)などのように、かつての祭日が現在の祝日に受け継がれている休日もあります。
【祭日から祝日になった日】
〇四方拝(しほうはい*旧・四方節)
1月1日(元日)
〇紀元節(きげんせつ)
2月11日(建国記念の日)
〇春季皇霊祭(しゅんきこうれいさい)
春分の日
〇天長節(てんちょうせつ)
4月29日(昭和の日)
〇秋季皇霊祭(しゅうきこうれいさい)
秋分の日
〇明治節(めいじせつ)
11月3日(文化の日)
〇新嘗祭(にいなめさい)
11月23日(勤労感謝の日)
以前は祭日とされていた日の中には、このように祝日として残っていているものもあります。
そのため戦前の世代の人が「祭日」という言葉を記憶しており、現在も祭日という言葉が使われていると考えられます。
昭和時代までは「祭日」をお祝いするために、家の軒先に国旗の日の丸を掲げる家庭も数多くあったそうです。
現在でも数は少なくなりましたが日の丸を掲げる家もありますし、バスやタクシー、鉄道などでは車両に日の丸を掲示している会社もあります。
祝日:日本の公式な祝日
祭日:皇室で執り行う宗教儀式を行う日
祝日は心も体も休めるよう過ごしたいものですね。