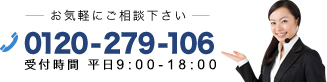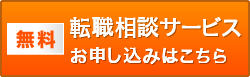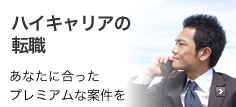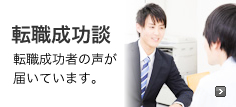人事異動とは?
転職雑記 2023/10/24

転職もそうですが、企業では店舗異動や部署異動など、これまで勤めてきた環境に大きな変化・変更が起きる場合があります。
多くの企業では、組織運営を最適な状態に近づけるために「人事異動」を行います。
この人事異動について「部署が変わるだけ」と思っている人が多いようですが、人事異動には様々な内容が存在します。
1.人事異動の目的
人事異動は事業活動における変化に対応し、効率的な組織運営の実現を目的に行われます。
適材適所の人員配置が実現し、組織の活性化、効率化が図られることが理想です。
・事業戦略の実現
経営をとりまく環境の変化が激しい現代、企業が事業戦略を実現するためには、組織変更は避けられないものです。
新規事業の立ち上げ、あるいは既存事業からの撤退などの場合には、人員を再配置する必要が生じます。
こうした事業戦略の実現には、人事異動が不可欠です。
・人材育成
人事異動は、人材育成を目的に行われる側面もあります。
定期的な「ジョブローテーション」により担当業務を変更し、幅広い経験をしてもらうことが目的です。
将来、経営の中核を担う人材には、社内のさまざまな部署や業務を経験してもらい、全社的な視点を養うことが欠かせません。
・組織の活性化
長期間にわたり「同じ部署で、同じメンバーが、同じ業務をする」ことは、一定水準の品質や安定した業績を維持するといったメリットがある一方で、変化が起こりにくい、変化を受け入れられない組織風土に繋がるなどのリスクも含んでいます。
考え方が固定化され、新たな発想やイノベーションが生まれるにくくなるのです。
また、同じ人物が一つの業務を長く担当することによる業務の「属人化」は、ときには非効率や不正のリスクの温床となります。
組織の淀みを解消し活性化するために、適切な人事異動が必要となるのです。
・人事異動の種類
「人事異動」は部署が変わるだけではありません。
なんとなく「部署が変わること」と思っている人は多いようですが、広い意味では採用や退職に関することも人事異動の一種です。
また異動の範囲が自社内にとどまらず、会社を跨ぐ場合もあります。
・部署異動
人事異動の多くは、所属部署が変更になることを指します。
例えば、営業部から総務部への所属部署の変更といった人事異動です。
計画的なジョブローテーションにより実施される形態ですが、ときには欠員対応などにより行われることもあります。
・転勤
転勤とは転居をともなう人事異動のことを指します。
業務内容は変わらず勤務地が変わる場合や、業務内容も同時に変わる場合も。
いずれにせよ転居をともなう人事異動は働く従業員にとって相応の負荷となるため、転居手当や単身赴任手当などといった福利厚生で支援する企業もあります。
・昇進
昇進とは、社内での職位が上がることを指します。
例えば、課長から部長へ昇進するという人事異動がこれに該当します。
・降格
降格とは、社内での職位が下がることを指します。昇進の逆となります。
・出向
出向とは勤務する会社に在籍したまま、一定期間、別の会社で勤務する人事異動を指します。
出向先の多くは自社の関連企業(子会社・親会社)になることが多く、給与などの労働条件は現在勤務する企業のものが適用されるケースがほとんどです。
・転籍
在籍している会社との雇用契約を解除して、異動先の会社と新たな雇用契約を締結し勤務する人事異動です。
給与などの労働条件は転籍先の制度が適用されることが多いようです。
・解雇
企業が従業員との労働契約を解除します。
懲戒解雇、整理解雇、普通解雇といった3つの種類があります。
・免職
「免職」は、国家公務員法や地方公務員法に規定されている懲罰のことを言います。
民間企業でこれに当るのが「解雇」です。
2.人事異動が多い時期
人事異動には一年を通して行なわれますが、一般的に行われる時期は、3月末やその会社の年度末に行なわれることが多い傾向にあります。
その理由は、次の年度に向けて組織や事業戦略の変更などを行いたい時期だからです。
また、節目やキリのよいタイミングで人事異動の旨を伝えられる方が、社員にとっても動きやすく、気持ちを新たにしやすいというメリットもあります。
3.人事異動は拒否できないが…
人事異動は、就業規則に定められている場合は業務命令となり、従業員は正当な理由なく拒否することはできません。
しかし、従業員を退職させることを目的に業務上の必要性や人選に合理性がない異動を命じるようなケースでは、人事異動が無効になる場合もあります。
他にも自主退社に追い込むために、閑職や慣れない業務に異動させるといったケースがこれにあたります。