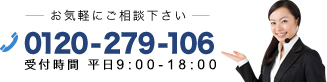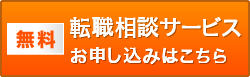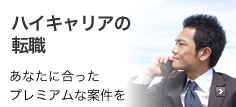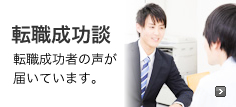内定通知書を受け取ったら確認すべきこと
転職雑記 2024/7/16
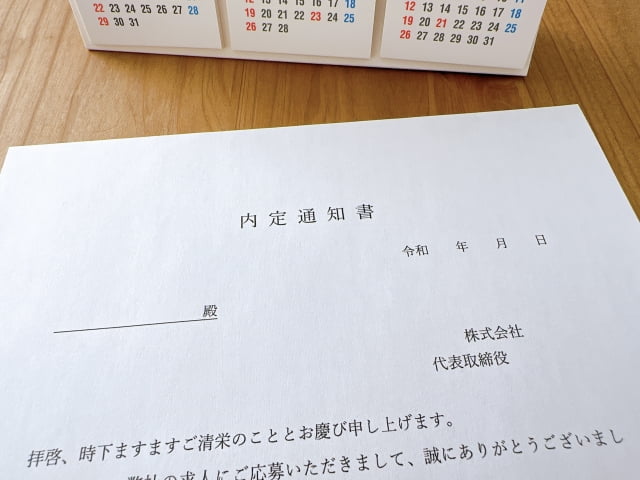
転職活動で、企業から『内定通知書』が送られてくる場合があります。
内定通知書とはその名の通り内定を知らせる書類ですが、いざ受け取ってみると何をすればよいのか把握していない人が多いようです。
今回は、内定通知書の内容や法的効力、受け取った後に確認するべき点などについてチェックしたいと思います。
1.内定通知書の概要
「内定通知書」とは、採用が決まった応募者に対して企業側が発行する書面です。
内定通知書の発行は法律で定められているものではないので、企業が独自に作成する書類となります。
記載内容に関しても統一されたルールはありません。
なお、内容については以下の項目の記載があるのが一般的です。
・採用が決定のお知らせ
・入社日
・就業場所
・入社日までに準備しておくもの
・内定取り消し事由
・内定承諾書の送付期限
・担当者、連絡先
など
2.内定通知書の法的効力
内定通知書そのものには法的定義はありませんが、労働契約には法的効力が発生します。
内定は、労働契約法第6条に定められている「労働契約の成立」に該当。
そのため企業が「内定通知書」を発行して該当求職者に内定を通知すると、労働契約の開始時期が決定することになります。
企業はトラブルが起きるのを回避するために内定通知書を発行しますが、求職者もできるだけ書面による通知を受けておきたいところです。
3.採用通知書との違い
『内定通知書』と似ている書類に『採用通知書』があります。
採用通知書は、企業が求職者に対して正式な採用を通知するための書類ですが、これも内定通知者と同様に法的な定義はありません。
いずれも企業の雇用意思を伝える書類であり、大きな違いはないと言ってよいでしょう。
ただ、書類の意味合いや採用プロセスは企業によって様々であり、この2つの書類を別々に発行しているケースもあれば、兼用して「採用内定通知書」として発行しているケースも見られます。
4.内定通知書を受け取ったらするべきこと
内定通知書を受け取ったら一安心ですが、まだ転職活動は終わりではありません。
以下を確認し、入社日まで気を引き締めましょう。
①記載内容の確認
まずは記載内容を確認します。特に「内定取り消し事由」が記載されている場合には、どのようなケースで内定が取り消される可能性があるのかを確認するようにしましょう。
また、雇用条件が記載されているケースもあるので、よく読んで納得したうえで内定を受諾するとよいでしょう。
②お礼の連絡
必須ではありませんが、採用担当者にお礼の連絡を入れると良い印象を与えられます。
連絡方法はメールや電話がベターです。
転職サービスを利用している場合は、そのサービス会社経由でお礼を伝えてもらうのもよいでしょう。
③内定承諾書の送付
内定承諾書は、あらかじめ定められた項目に記載し、署名捺印して返送するのが一般的です。
内定通知書を受け取った年月日と住所・氏名欄などが空欄になっているので、空欄を埋めて提出するようにしましょう。
企業名は省略せずに正式名称を、人事部などの部署も確実に記入してから送付します。
④内定承諾および辞退の連絡期間について
内定に対する返答は1週間以内に連絡するのがベターですが、企業によっては内定の承諾・辞退の連絡期限を設けているケースもあるので、その場合は設定された期限に連絡をすべきでしょう。
期限内での回答が難しいと予め判断できる場合は、可能な限り早めに相談し、トラブルの芽を摘んでおくことをオススメします。
5.内定を辞退したい場合
内定通知書が届いたものの、他の企業からも内定を得ているために辞退したいケースもあるでしょう。
内定辞退のマナーなどについては以下の通りです。
・内定辞退の申し入れ
民法第627条では、期間の定めのない雇用解約の申し入れについて、「いつでも解約の申入れをすることができる」としており「解約の申入れ日から2週間を経過することによって終了」します。
内定承諾書を提出した後であっても内定辞退から2週間たてば契約解除されますし、たとえ企業側が承諾しなかったとしても法的には問題なく辞退できます。
・内定辞退のマナー
内定辞退が可能とはいえ、企業側は採用者の人数を含めて事業計画を立てていますから、早めに知らせるのがマナーです。
特に中小企業の場合は採用人数が少ないため内定辞退の影響は大きい場合があります。失礼のないように丁寧に伝えるようにしましょう。
6.まとめ
・内定通知書がなくても法的に問題はない
・内定通知書が発行されるかどうかは企業により異なる
・内定通知書の発行をもって労働契約の開始時期が決定する
・内定通知書は送付されてきたら内容をしっかり確認する
・内定に対する返答は1週間以内がベター
内定通知書を受け取り、その内容に疑問や違和感があった場合は、企業の採用担当者に連絡し質問や相談をされることをオススメします。
承諾するにしても辞退するにしても、悔いを残さない選択にしましょう。