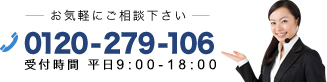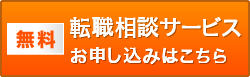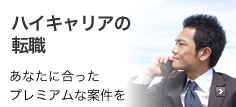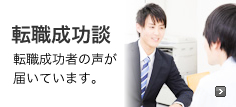解雇と退職の違い
転職雑記 2024/12/10

『解雇』とは、会社が従業員と結んでいる労働契約を一方的に終了させることを言います。
解雇は従業員の生活に多大な影響があるため、法律で一定の規制が設けられています。
1.解雇とは
解雇は従業員に対し会社が一方的に労働契約を解除することですが、各種の法律によりさまざまな規制が設けられています。
労働契約は、解雇以外にも雇用期間の満了や企業の倒産によっても解消します。
また、雇用の期間を定めていない場合は、会社側の意思表示によって任意に解消できます。
なお、従業員からの申し出で雇用契約を終了する場合は『退職』となり、解雇とは言いません。
2.解雇と退職勧奨の違い
解雇と似た言葉に『退職勧奨』があります。
退職勧奨は、会社が従業員に退職するよう説得して退職してもらうことを言います。
あくまで従業員の意思で退職してもらう方法ですので解雇とは異なります。
厚生労働省によれば、退職勧奨とは『使用者が労働者に対し「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言って、退職を勧めること』としています。
また、『労働者が自由意思により、退職勧奨に応じる場合は問題となりませんが、使用者による労働者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たるとされる場合があります』としています。
なお、退職勧奨に応じて退職した場合には、『自己都合』による退職とはなりませんので注意が必要です。
3.解雇の種類
解雇は大きく『普通解雇』と『懲戒解雇』に分けられます。
さらに普通解雇の中には特別なものとして整理解雇があり、その他に諭旨解雇があります。
・普通解雇
普通解雇は、懲戒解雇や整理解雇以外の解雇の総称です。
普通解雇の事由としては、従業員の勤務態度が悪い、能力不足、私傷病などによる労務不能、重大な業務命令違反などが挙げられます。
・整理解雇
整理解雇は、会社の経営状態が悪く人件費を削減せざるを得ない状況のときに行うものです。
一般的には『リストラ』とも呼ばれます。
ただし、人員削減を目的とした解雇が、すべて有効な整理解雇とされるわけではありません。
整理解雇では有効性が厳しく判断されます。
・論旨解雇
諭旨解雇は、従業員への懲戒の一つで、懲戒解雇に相当する従業員について、それまでの功績や将来などを考慮し懲戒解雇という重い処分を避けるときに行われることが多いものです。
懲戒解雇より一段軽い措置として行われます。退職金が支払われるケースもあります。
・懲戒解雇
懲戒解雇とは、従業員への懲戒処分としては最も重いものです。
重大な規律違反が解雇事由になりますが、その内容は業務上横領、無断欠勤、セクハラ・パワハラ、経歴詐称などです。
退職金が支給されないことが多く、再就職時に不利になるなど重い処分となります。
4.正当な解雇理由がない場合は解雇できない
労働契約法の第16条では、解雇について次のように規定しています。
『解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする』
使用者に解雇の意向があったとしても、その理由が『客観的に合理的』と認められない場合、労働者を解雇することはできません。
この『客観的に合理的』とは、社会の常識に照らして納得できる理由のことで、誰もが「解雇するのが妥当」とされる内容でなければなりません。
また、解雇には就業規則や労働契約書などによる根拠も必要です。就業規則などに規定し、労働者に周知していない場合は解雇できないのです。
5.解雇制限
正当な理由があっても、解雇されないケースがあります。
以下の2つの期間については、労働基準法により解雇が禁止されています。
これを『解雇制限』と言い、労働基準法第19条に定められている「特定の条件に該当する労働者の解雇を制限する期間」を指します。
業務上の傷病のため療養する期間およびその後30日間
産前産後の休業期間およびその後30日間
なお、『業務上の傷病休業者』については、解雇制限に該当しても除外となる場合があります。
これを『解雇制限の除外』と言います。
・解雇制限の除外
①労働基準法上の打切補償として平均賃金の1200日分を支払った場合、あるいは打切補償の支払いに代えて、従業員の治療開始から3年経過時点で傷病補償年金が支給されている場合
②天災事変により事業の継続が不可能になり、労働基準監督署の認定を受けた場合
解雇は、相応の事由や状況がない限り、事業者が安易にできるものではありませんが、まずは内容を十分に理解しておくことが必要です。