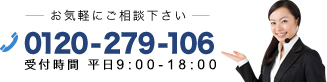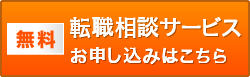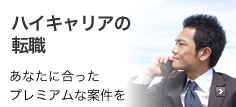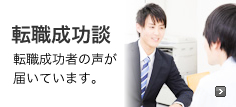パチンコホールの「マル優」店舗が減少していく背景を考える
パチンコのユルイ雑学 2021/8/3

皆さんはパチンコ店の「マル優」マークを見たことはありますか?
正式名称は「特例風俗営業者」。通称「マル優」と呼ばれているもので、長年違反無く優良な営業を続けている風俗営業者に対し、その遵法意識を評価して、店舗運営で優遇措置を受けることが出来るという制度です。
一般的に例えるなら、運転免許の「ゴールド免許」とでも言えば良いでしょうか。店内に「マル優」認定書を掲示している店舗もありますね。
マル優の認定はパチンコ店に限らず風俗営業であれば対象になりますが、認定店舗の半数以上はパチンコ店が占めていました(例:平成23年末時点の認定店846店のうち、パチンコ店は486店舗)。
しかしながら近年、パチンコ店におけるマル優マークの認定店舗が激減しているのです。
パチンコ店における特例風俗営業者(マル優)の認定店舗数は、平成23年(2011年)の486店舗をピークに7年連続で減少。
「マル優」制度は平成10年(1998年)の風営法の改正で登場して以来、認定店舗は増加して来ました。しかし、平成24年(2012年)に広告宣伝規制などの強化によって、同年だけでも137店舗の大幅減になり、以降も減少し続けたわけですが、2019年時点でようやく下げ止まり、当時で178店舗という状況でした。
そもそもマル優の認定を受ける要件は厳しく、その要件は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法、風適法)の第十条の二「特例風俗営業者の認定」にあります。
①許可を受けて風俗営業を営んで10年以上経過している。
②過去10年以内に、風営法の処分・指示を受けたことがない。
③管理者講習をきちんと受けている。
要件の一つは営業を始めてから10年ですから、認定を得るにはなかなかハードルが高いものです。
では特例風俗営業者に認定されると、どんなメリットがあるのでしょうか?
以下がその優遇措置です。
【特例風俗営業者のメリット】
①2回目以降の管理者講習の免除
通常管理者は、3年に1回程度の管理者講習を受講しなければならないのですが、マル優認定を受けると2度目以降の受講が不要になります。(※同一店舗・同一の管理者に限る)
②店内改装が、事後の届出でもよくなる
店内の構造を変更は事前に変更承認の申請をしてからの着工となり、完了後も警察のチェックの上でOKが出て初めて営業を再開できます。
OKがでるまで営業出来ないのですが、これが事前承認無しで着工し、事後に届け出ればよくなります。
営業を止めることなく構造変更できますから、これは大きなメリットといえるでしょうか。
③マル優の認定証を店内に掲示できる
警察署からの「優良店舗≒健全なお店」としてのお墨付きですから、多少なりとも対外的なアピール要素にはなるとは思います。
④遊技機の認定申請の際に添付する保証書を管理者が作成できる
遊技機取り扱い主任者の資格を持つ管理者に限ります。
このようなメリットがある特例風俗営業者ですが、近年は取得申請するパチンコ店も減少しています。
さらに、最も大きいメリットであるはずの構造変更の事後承認が、形骸化していることが最大の要因かもしれませんね。
個人的には「マル優店舗だからその店舗で遊ぶ」ということはなく、マル優マークがある店舗であっても、遊技空間や環境が整っていないとか、そもそもの本質的な魅力(来店動機に繋がる要素)がなければ、遊びには行かないです。
パチンコ店の管理者の方もそんなことは百も承知でしょうし、要件を満たしていても取得メリットが弱いのであれば、本質的な要素、他の項目にコストを割く、ということなのではないでしょうか。
これからも減少し続けるかもしれませんね・・・。