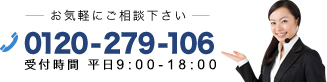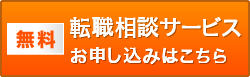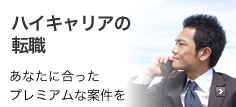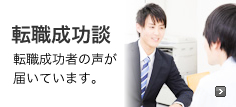三六協定とは
転職雑記 2023/2/9

三六協定とは、「時間外労働」に必要となる労使協定です。
労働者にとって重要な協定ですが、その内容についてはあまり知られていません。
求人情報の中で、時間外の労働条件は重要な項目の一つですから、転職を考えている人は詳細を知っておきたいところです。
1.三六協定の概要
三六協定は「さぶろくきょうてい」と読み、「時間外・休日労働に関する協定届」のことを言います。
名称の由来は労働基準法の第36条を根拠とする労使協定だからです。
労働基準法では、会社は原則として1日8時間・1週間40時間を超えて社員を働かせてはならないと定められています。
その時間以上に残業や休日出勤が発生する場合には、別途労使協定を締結しなければならないという規定が労働基準法36条に定められています。
2.「労使協定」とは?
36協定は「労使協定」の一種です。労使協定とは会社(使用者)と社員(労働者)との間で結ぶ協定のことです。
労使協定は、「労働者の過半数で組織する労働組合」か、それがない場合は「労働者の過半数を代表する者」との間で協定を結ぶことになります。
労使協定は会社単位ではなく、事業所ごとに締結されます。
3.時間外労働の限度
36協定を結んだからといって、いくらでも働かせて良いということはありません。
協定の中で時間外労働時間の上限が定められています。
この上限の時間数は会社によって異なりますので、詳しく知りたい場合は、内定後の処遇面談の機会などで確認してみると良いでしょう。
なお、厚生労働省が定める延長時間(時間外労働時間)の限度は以下のように定められています。
1週間当り 15時間
2週間当り 27時間
4週間当り 43時間
1ヶ月当り 45時間
2ヶ月当り 81時間
3ヶ月当り 120時間
1年当り 360時間
(一般労働者の場合)
この限度時間を超えるような時間外労働時間が設定されている場合は、違法となる可能性が高くなります。
時間外労働のルールをチェックする意識を持たないと、単なるサービス残業となります。
4.「特別条項」付き協定
三六協定を結ぶ場合は、原則として上記の限度時間内に収まるようにしなければなりません。
しかし、急なトラブル対応や繁忙期忙といった「特別な事情」を理由に、通常の三六協定と合わせて「特別条項付き三六協定」を結んで対応することもできます。
これを「特別条項」と言います。
「特別条項」は、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に、特別条項付き協定を結んで限度時間を超える労働時間の延長が可能です。
もちろん特別条項にも労働時間の上限が設定されています。
2019年4月から施行された改正労働基準法で上限は以下の通りです。
①時間外労働が年720時間以内
②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
③時間外労働と休日労働の合計について、2~6カ月平均80時間以内
④時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6カ月まで
【求人情報での特別条項の記載例】
求人企業に「特別条項」付の36協定がある場合、求人情報では以下のような記載になっていますので、チェックしてみましょう。
[勤務時間]
就業時間:8時45分〜17時00分
時間外労働時間あり
月平均時間外労働時間:10時間
36協定における特別条項:あり
[勤務時間]
就業時間:8時30分〜17時00分
時間外労働時間なし
36協定における特別条項:あり
特別な事情・期間等:臨時的な受注の増大や集中により納期がひっ迫した時、6回を限度 に月80時間、年600時間まで延長することができる。
[勤務時間]
時間外労働時間なし
36協定における特別条項:あり
特別な事情・期間等:時間外労働無し
5.その会社はブラック企業?
このように時間外や休日労働の可能性がある場合には三六協定の締結が必要ですが、実際には協定そのものがなされていなかったり、適正に運用されていなかったりという例も多くみられます。
現在では「サービス残業」といった言葉も定着しているように、超過勤務や残業代が適切に支払われないという事案がニュースなどで盛んに報道され、従業員からの訴訟も増えています。
もし自分の職場でサービス残業が多い、あるいは時間外手当が十分に支払われていないと感じられる場合には、会社で三六協定が正しく運用されているかを確認することをおススメします。